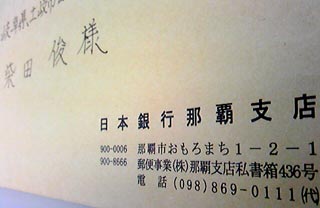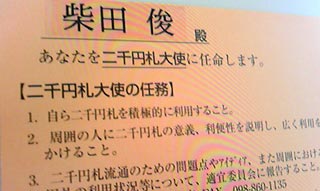ここ数ヶ月、ブログのアクセス数が着実に増えてきています。少ない月でも、1ヶ月で6000ページビュー、3000ユーザーは下回らないようになりました。
その内容をもう少し詳しく見てみると、検索されて初めて私のブログにたどり着く人は、「ソフトバンクホームアンテナ」や「Thinkpad T43p」というキーワードの人が多いです。その人達は、該当ページのみを見るだけなので、直帰率は80%を超えます。
一方で、水泳関連のキーワードでたどり着く人たちは、関連するページをよく見ています。「岐阜 水泳 大会」などで検索してきた人たちの直帰率は40%以下で、平均ページビューは、3を超えます。
・・・この文章の意味が分からない経営者の方、すぐに本屋さんで、ホームページのアクセス解析についての本を購入して勉強されることをオススメします。ホームページは、どんな人がどんな考えを持って見ているのかが、非常によく分かる媒体です。それに合わせてホームページを変更してゆくことで、アクセスが増えて、業績改善にもつなげられます。
ちなみに、私のブログの場合、ソフトバンクホームアンテナのことが書いてあるページに、それに関連するページへのリンクや情報を増やすことで、よりアクセスが増え、また、それに関連するサービスの案内などを付ければ、そこから申し込みなども期待できます。
水泳関連のページについては、水泳関連のグッズの販売などを付けるとそこから申し込みが期待できます。ただ、水泳に関しては、ただ商品へのリンクを付けてもダメです。もっともっと、見ている人が興味を抱くような情報を加えることで、信頼が得られてからビジネスにつなげた方がよいです。例えば、水着についても、ただ最新の高速水着へのリンクを付けるのではなく、実際に使った感想や、注意点、他の人たちの意見などもドンドン載せて、メーカーの商品案内ページでは得られない情報を得られるページとして定着させることが重要です。
一般的に、会社の経営者が実名でブログを書く場合、ビジネスにとってのメリットを期待して書いているはずです(私の場合、大半は自己満足というか、好きで書いている部分がほとんどですが)。ぜひ、戦略を立ててブログを書かれることをオススメします。
もっと具体的に、どうしたらよいのか聞きたい場合、IT系に強いコンサル会社や、地域力連携拠点(無料)などで相談してみてはいかがでしょうか?岐阜県東濃地方の方は「地域力連携拠点東濃」にご相談ください。